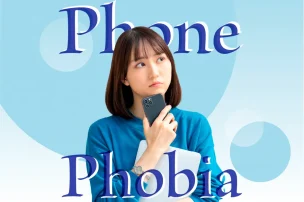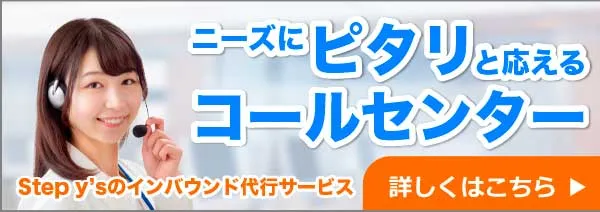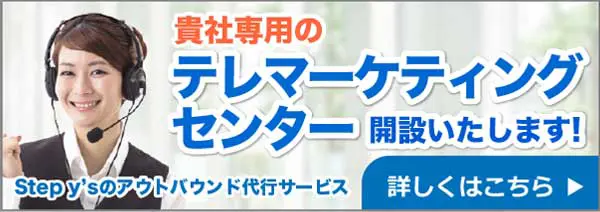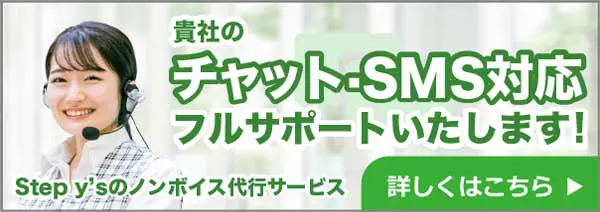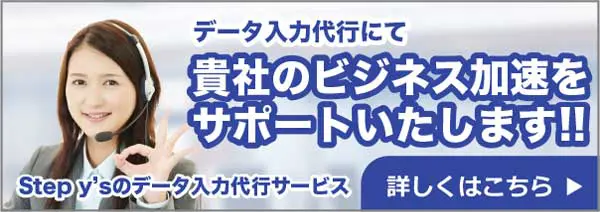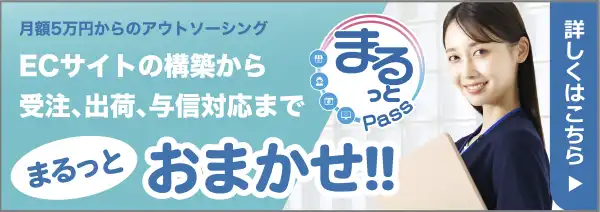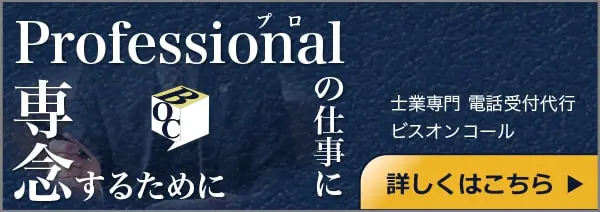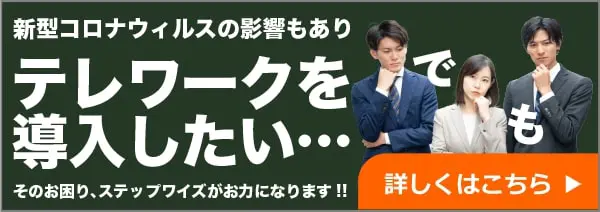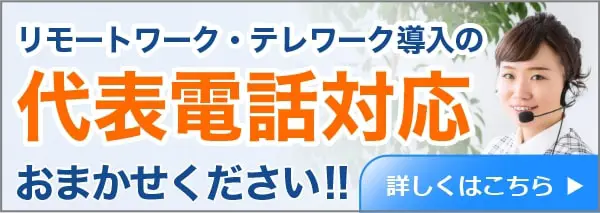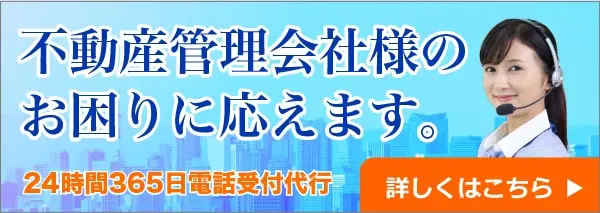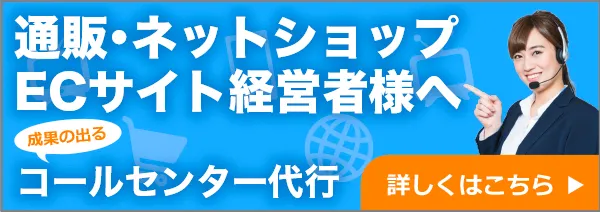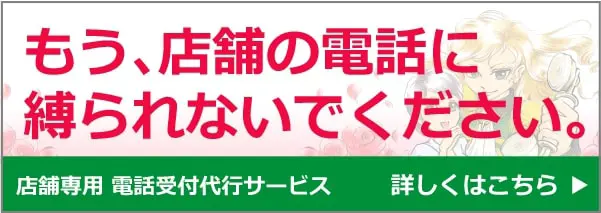近年、ビジネスネームという言葉をよく目にし、導入を開始する企業が増えていると感じることはないでしょうか。多様な働き方や個人情報保護の観点からも注目され、社内外での新しいコミュニケーションの形として定着しつつあります。
一方、「そこまでしなくても」「社内で混乱が生じないか」という懸念の声もあります。
しかし実際には、ルールの明確化や周知を徹底することでスムーズな運用が可能となり、導入による混乱は最小限に抑えられます。
当社Step y’sでも2025年6月、本格的なビジネスネーム導入をスタートいたしました。
従業員の個人情報保護をはじめ、カスタマーハラスメント対策を主とする従業員の安心・安全な労働環境の整備とより円滑な顧客対応を目的としての導入でしたが、計画的に準備をしたことで大きな混乱もなく運用を継続しています。
ビジネスネームの導入をお考えのご担当者様やビジネスネームについて興味がある方は、ぜひ当記事を読んでいただき、参考にしてください。
目次
ビジネスネームとは

ビジネスネームとは仕事で使用する、戸籍上の本名とは異なる名前のことです。
BusinessとNameを合わせた和製英語で、ペンネームや芸名などと同様のものとされています。
公的な書類には使用できませんが、名刺や屋号、社外とのコミュニケーションに使用することは制限されていません。広い意味では結婚などで姓が変わっても旧姓のまま勤務を続けることもビジネスネームを使用していると言えるでしょう。
ビジネスネームが社会に広まった背景
2000年代に入ると住民基本台帳を悪用した事件や、教材販売会社の個人情報漏洩事件などが大きく報道され、2005年に個人情報保護法が全面施行されました。
従業員の名札から名前を検索してSNSのアカウントを特定したり、口コミに個人名を記入し批判的な内容を投稿するといったトラブルが発生する事例もあり、危機意識の高まりとともに、主に従業員の安全を確保する目的で「本名ではなく業務用の名前やイニシャルで応対する」スタイルが一部業界で導入され始めました。
SNSや報道機関でビジネスネームを採用している企業があると紹介されたことがきっかけに、特に飲食店や宿泊施設、小売、美容関係など接客を必要とする業界で積極的に導入され、電話のみの接客であるコールセンター業界でも次第に導入が進められてます。近年注目されているカスタマーハラスメント(カスハラ)防止や従業員のメンタルヘルス対策の一環としても有用だと、従業員採用時のアピールポイントとしても注目されています。
企業としても従業員を守るために、安全配慮義務を果たす必要があります。
精神的な健康を害することがないよう、本名かつフルネームで対応するよう強要することは難しくなってくると考えられます。

コールセンターにおけるカスハラとは?対応の方法と対策についてご紹介!
なぜビジネスネームを使うのか
ビジネスネームの活用には、単なる形式の変更にとどまらない、さまざまな目的と背景があります。
では、なぜ多くの企業がこの仕組みに注目しているのでしょうか。その理由を紐解いていきましょう。
個人情報保護の観点
昨今、インターネットで名前を検索をすると本名で使用することを推奨したSNSや、学生時代の大会の記録などが確認でき、個人の生活状況が簡単に調べられるようになりました。
勤務中の名札やレシートなどで従業員の氏名を把握した利用客が、悪意を持って様々な方法で自宅や交友関係を把握し、ストーカー行為を行う事例も少なくはありません。
こういった被害を防ぎ、従業員が安心して業務を行うためにビジネスネームの利用を決定した企業も多いでしょう。
精神的な距離感の調整
人間関係の距離感は、業務中のコミュニケーションにおいて非常に繊細な要素です。親しみを込めて敬称を変えたり、ニックネームで呼び合うことで関係が近づく場合もあれば、逆にその“近さ”が負担になることもあります。
ビジネスネームは個人の精神的な距離を適切に保ち、相手との関係性をスムーズに保つ手段として役立ちます。
覚えやすさ、聞き取りやすさを重視
馴染みのない珍しい苗字や発音がやや難しい名前のため、いつも間違えられたり何度も繰り返し名前の確認をされるといった場合、説明を行う従業員にも精神的負担が生じることもあります。
特に接客や電話応対においては、担当者名を正確に聞き取れなかったことによって対応が滞ってしまうケースもあります。
聞き取りやすく、覚えやすいビジネスネームにすることで苗字、名前の聞き取りにくさから発生するトラブルを未然に防ぐことができます。
業務中とプライベートを切り分けやすくなる効果
「公私の区別」を主目的としてビジネスネームを導入した事例もあります。
会社は舞台、従業員は役者と位置付けることにより、気持ちのスイッチを切り替えたり業務における目標を達成するための役割やマインドをイメージする土台としても活用されています。
また、本名はプライベートのみで使用するという線引きができ、仕事の時間以外は自身や家庭のことを大切にするといったメリハリのある業務が期待できます。
マイノリティ(少数派)への配慮
マイノリティ(少数派)に配慮する目的でビジネスネームを導入するケースもあります。
「戸籍上の氏名」と当人とのギャップによる苦痛をなくし、個人の人格や人権を尊重することで、抑圧されることなく活躍できるよう、職場環境を整えます。
離職防止・定着率向上
個人情報保護の観点の他、多様性を重んじる、従業員の精神的負担に配慮するなど、いきいきと活躍できる職場環境を提供することで、離職防止・定着率向上につながることが期待できます。
ブランディング目的
個人名だけでなく、社名やブランド名、商品名など、名前から受ける印象は思いのほか大きな割合を占めます。
名前から得られる印象を活用するため、インパクトのあるビジネスネームを導入している事例もあり、名刺交換時に話題づくりのきっかけとなる、すぐに名前を覚えてもらえるといったメリットもあります。
商品のイメージに合わせたビジネスネームを持つことで、ブランドイメージの統一化を図ることも可能でしょう。
ビジネスネームの使用が向いていない職種もある
医師や薬剤師、弁護士など国家資格が必要な専門職はビジネスネームでの資格取得が認められていないため、書類や掲示物に本名の明記を求められるシーンが多く、自由度が限られます。
そのため、ビジネスネームの活用があまり浸透しておらず、実用性の面でも慎重な運用が必要とされています。
ビジネスネーム導入の手順と運用方法

ビジネスネームを導入するにあたり、事前準備や運用方法について思案している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、スムーズな導入と混乱を来さないためのルール作りについて解説します。
1.ビジネスネーム導入の目的を考える
上記で紹介したように、ビジネスネームは様々な目的で導入されています。
目的を明確にすることで、社内外への説明や名付けのルール化をスムーズに行うことができます。
2.名付けのルールを決める
導入の目的が決定すると、名付けのルールも方向性が明確になります。
プライバシー保護や聞き取りやすさを目的とした場合は一般的で馴染みのある苗字と名前、もしくはイニシャルにする。「ニックネーム」を導入する際は、お客様との距離感を近づけたい、商品名や店舗に沿ったブランディングを目的とするなど、方向性を統一し、自由に名前を決めないよう、ルール作りをしましょう。
また、商標や著名人と同じ名称を使用しないよう、注意することも求められます。
3.管理・確認方法を決める
ビジネスネームを導入すると他部署との連携や、戸籍上の氏名を使用する労務関係の手続きで混乱が発生することが予想されます。ネームリストを作成するなど、内部で確認と管理がしやすい体制を整えます。変更希望や退職があった際もどのように対応、周知するかあらかじめ決めておきましょう。
4.トラブルを想定し、対応方法を決定する
引き継ぎがスムーズにできない、クレームが発生した際の対応者がわからないなど、ビジネスネームを導入したことによって発生すると考えられるトラブルをあらかじめ想定しておき、対応方法を決定します。
実際にトラブルが発生した際の不手際によって、お客様にご迷惑をかけないよう対策をしておくことが大切です。
5.従業員の意向を確認する
突然「ビジネスネームを導入します」と周知しても、そもそもビジネスネームとは何か知らない従業員がいる可能性があります。
ビジネスネームとは何か、何のために導入するのか、いつから開始したいのか、決定事項や社外へのお知らせ方法について説明を行い、ビジネスネームにしたいか、本名を継続して名乗りたいか、意向を確認します。
6.社外に周知する
ビジネスネーム導入で懸念されることのひとつに「クライアントとの信頼関係」があります。ビジネスネームを導入する場合は事前にお知らせし、クライアントに迷惑が及ばないよう注意しましょう。
お知らせを行う場合は、導入する目的やご連絡時に支障が出ないこと、トラブル時の対応方法なども併せて説明し、一方的な通知にならないように配慮する他、クライアントの意見も伺いましょう。
また、自社のWebサイトなどで広く周知することも大切です。
クライアントやお客様にご理解いただく他、従業員を守ることに配慮している企業というイメージがつき、求職者へのイメージ向上にもつながりますので、欠かさずアピールしましょう。
導入後の運用方法

ビジネスネームをただ導入しただけで終わらせず、導入後もスムーズなコミュニケーションを行えるよう、以下の点に注意し、継続的に運用できるよう対応しましょう。
社内でのネームリストを最新の状態に保つ
ビジネスネームの変更や新規追加があった際は、速やかにネームリストを更新しましょう。また、期間を決めて定期的に見直しを行い、リストに相違がないか、確認を行うことも大切です。
常に最新の状態を保つことで、誤認や混乱を防ぐことができます。
いつでも確認できる状態にする
連絡先一覧や社員リスト、組織図など社内で社員情報を確認できるものにビジネスネームを併記し、確認できる環境を整えておきましょう。
新規のクライアントにも説明する
社外の取引先や新規クライアントとのやり取りにおいても、ビジネスネーム制度を導入している旨を初回に伝えましょう。
Webサイトなどに掲載しているからといって、必ず目を通しているとは限りません。導入理由も併せて説明することで、誤解や不信感の防止につながります。
新入社員へ入社時に説明する
新入社員には、制度の目的や使い方やルールを入社時の研修やオリエンテーションで説明します。社内文化として定着させるためにも、早い段階で理解してもらうことが重要です。
コールセンターにおけるビジネスネーム活用方法
コールセンターにおいてもビジネスネームの導入が進んでいます。
当社Step y’sでのビジネスネーム活用方法をご紹介いたします。
旧姓のまま勤務
入社後に入籍し、姓が変更したスタッフの希望に応じて旧姓のまま勤務を継続を許可しています。旧姓のままでの勤務継続は多くの企業で浸透している考え方ですが、これも広義的にいえばビジネスネームとして捉えられます。
同姓が複数名いる場合の対策
Step y’sは女性9割という従業員割合と、国内8拠点のコンタクトセンターで密に連携をとってサービスを展開しています。同姓オペレーターが複数いると、対応者の判別が難しく、該当者のみフルネームでの対応も不公平感を与えてしまうため、ビジネスネームにて判別し、確認に時間を費やすことの無いよう業務を行なっています。
カスタマーハラスメント(カスハラ)・クレーム対策
コールセンターという業務の性質上、温度感の高いお客様の対応を行う機会も発生してしまいます。
「フルネームを教えろ」「名前、覚えたからな」といった発言を受け、オペレーターが恐怖を覚えるシーンもありましたが、ビジネスネームを利用することによって「フルネームを伝えることに抵抗がなくなった」「出社が怖い、電話が怖い、といったことがなくなった」といった意見があり、離職率の低下にも役立っています。
信頼は“本名”ではなく、“安心”から生まれる

ビジネスネームは多様な働き方を実現するための一助となり、今や職場環境を整えるための手段とも言えるのではないでしょうか。
スタッフの安心感とお客様への信頼感を両立させるためには、仕組みづくりをしっかり行うことが求められますが、クリアしてしまえばコンプライアンスと従業員ケアのバランスを取る一手として有用であり、求職者へのアピールポイントとしても活用できます。
これを機会に導入を検討してみてはいかがでしょうか。
従業員の安心とお客様との信頼の両立を、Step y’sがサポートします
Step y’sではコールセンター業務を中心としたBPOサービスを提供し、多くの企業の発展を陰ながらサポートし続けております。
電話応対をはじめ、お問合せフォームやSMS対応、データ入力、白ナンバー車を対象としたアルコールチェック代行など、貴社の優秀な人材をコア業務に専念させるための多様なサービスを展開しており、ビジネスネームを導入されている企業においても柔軟に対応いたします。
ご相談・お見積りは無料となっておりますので、どうぞお気軽にお問合せください。